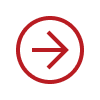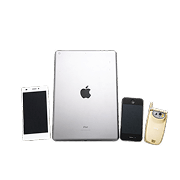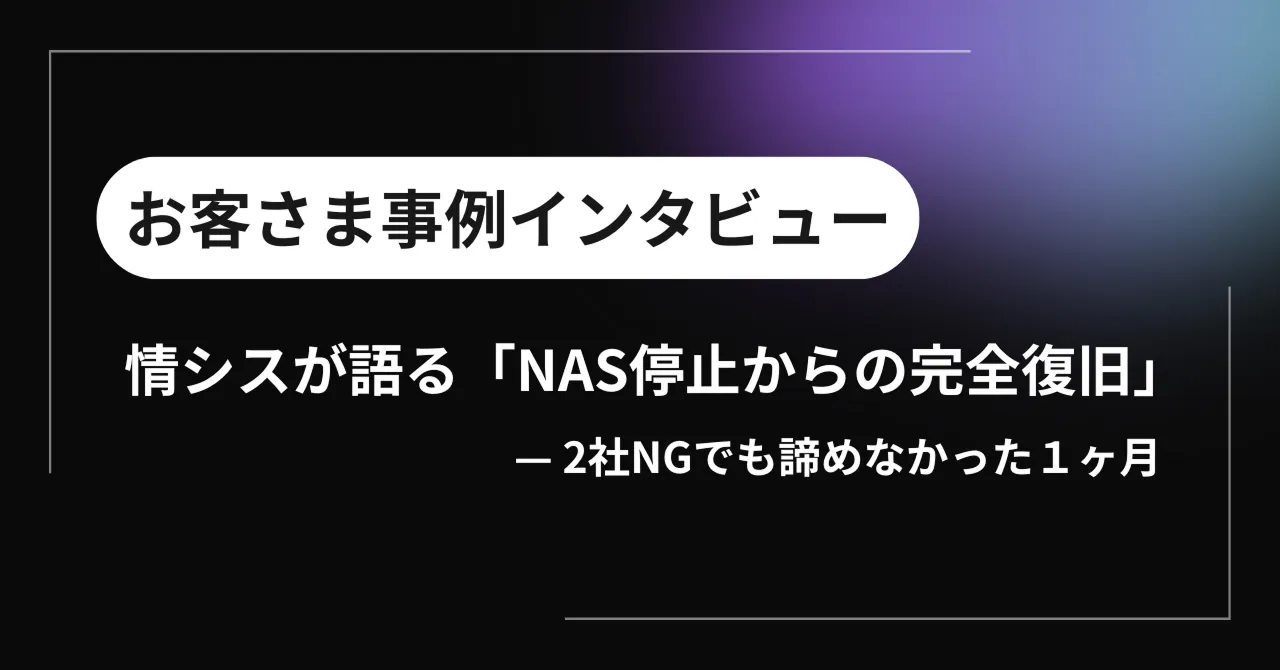
CUSTOMER
Interviews
情シスが語る「NAS停止からの完全復旧」
— 2社NGでも諦めなかった1ヶ月
| ご利用サービス | NAS データ復旧サービス、超特急サービス |
|---|---|
| 作業期間 | 初期診断:1日 復旧作業:1日 |
| 筐体種類 | NAS |
| メーカー | アイ・オー・データ機器 |
| 型番 | HDL-AH1.0 |
人事・採用を含む機密データを載せた基幹系NASが突然停止。2社から「復旧不可」。役員への週次報告が続く中、3社目で完全復旧に至るまでの1ヶ月と、その後の再発防止策を、情シス担当Yさんが具体的に語ります。
「デスクトップのショートカットが使えません」
利用部署からの一本の連絡が、情報システム担当Yさんにとって、1ヶ月に及ぶ格闘の始まりでした。企業の根幹を支える重要データが、突如としてアクセス不能に。2社の復旧業者に断られ、最悪の事態を覚悟したYさんを救ったのは、3社目の復旧業者、AOSデータ復旧サービスセンター(DATA119)でした。
1. 悪夢の始まり— 予期せぬNAS停止
「利用部署から『デスクトップに設置してあるショートカットが使えない』という申告がありました」
2025年4月中旬、Yさんが管理する人事部門の専用NASで異変が発生しました。約7台の端末で共有していたNASサーバーへのアクセスが、突如として不能になったのです。 このNASサーバーは、人事部門の業務専用に設置されたもので、極めて限られた端末からのみアクセス可能な環境でした。
このNASサーバーは、人事部門の業務専用に設置されたもので、極めて限られた端末からのみアクセス可能な環境でした。
「人事に関わる限られた端末でのみアクセスできる、専用のNASサーバーでした」
想定を超えた被害の全容
「当初は、単なるログデータ程度だと認識していたんです。ところが実態を確認すると...」
Yさんが現場を確認して愕然としたのは、保存されていたデータの重要度でした。人事データ、採用関連の重要情報など、企業の根幹に関わるデータが格納されていたのです。
「年月を重ねるにつれて利用用途が広がっていたようです。実態を我々の方で把握しておらず、かなり大事なデータだということで驚きました」
データ消失の影響範囲
Yさんは直ちに影響範囲の確認を開始しました。
「データがなくなったらどうなるか、影響を確認しました。毎月の情報確認とか、そういったところに関わってくること。あとは外部組織の方から問い合わせがあった時に、データを取り出せるようにしなくちゃいけないなと」
最も懸念されたのは、データが必要になるタイミングです。
「5月下旬には必要になるということで、ゴールデンウィークも挟むため、急いで現状把握を進めました」
時間との戦いが始まりました。
2. 自力での診断 - 絶望的な状況

情報システム部門の責任者として、Yさんはまず自力での診断を試みました。NASサーバーの状態を一つひとつ確認していきます。
「まず、機器の状態を確認しました。電源が入るかどうかを確認しましたが、電源は問題なく入りました」
次に、ネットワークの疎通確認です。
「そのNASサーバーに対して、同じネットワーク内の端末からPing処理を行いました。そちらも通っていました。基本的なところまでは問題なかったんですが...」
しかし、ここから異常な症状が次々と明らかになります。
診断結果
- ✓ 電源は入る
- ✓ Ping疎通は確認できる
- ✗ 実際のエクスプローラーでのファイルオープンができない
- ✗ ブラウザ経由でUIを開こうとしても開けない
- ✗ 正常なシャットダウンが不可能
フリーズ状態のNAS
特に深刻だったのは、シャットダウンの異常でした。
「NASサーバーは本体側で電源のシャットダウンを実施できるんです。通常なら電源周りのランプが点滅して、シャットダウンの作業が完了したら電源が落ちるはずなんですが、今回は全く落ちませんでした」
Yさんはフリーズ状態だと判断しました。もはや選択肢はありません。
「この状況ではどうしようもないということで、電源ボタンを長押しして、強制的に停止させました」
ハードディスクの異変
筐体を開けて、さらに詳しく確認します。
「NASサーバーの中身を確認しました。ハードディスクに外傷がないかというのを、見た目で確認しました」
外見上は問題ありません。しかし、決定的な異常に気づきます。
「確認したところ、ハードディスクから音が鳴っていなかったんです。通常、ディスクが回転する音や駆動音がするんです。電源は入っているのに、その音が一切聞こえませんでした」
慎重な切り分け作業
Yさんは、冷静に原因の切り分けを試みます。
「ハードディスクの故障である可能性が高いと思いました。ただ、筐体であるNASサーバー本体の方も故障している可能性を疑っていました」
問題がハードディスクなのか、それともNASサーバー本体なのか。この判断は、今後の対応を左右する重要なポイントです。
「予備のNASサーバーがありましたので、ハードディスクを差し替えて接続し、UIが開けるかどうか確認しました」
しかし、結果は芳しくありませんでした。
ーー「ディスクが読み込まなければUIは立ち上がらないということは、後でわかりました」
専門業者への依頼を決断
あらゆる手段を尽くしましたが、自社での復旧は不可能でした。
「この状況では、もう自力ではどうにもできないとなりました。そこで今回、専門のデータ復旧業者を選定させていただくという運びになりました」
Yさんの長い格闘が、ここから始まろうとしていました。
3. 復旧業者への依頼 - 2度の失敗

1社目の依頼(4月21日)
自社での診断が限界に達したYさんは、インターネットで復旧業者を探し始めました
「IOデータのNASサーバーに対応できるかというところで、『IOデータ NASサーバー データ復旧』という形で確認したかと思います」
Yさんが重視したのは、単なるハードディスクの復旧ではありませんでした。
「ハードディスクだけでなく、NAS全体の復旧が必要でした。NASには専用のOSが入っていますので、それも含めて復旧していただけるのかというところまで確認する必要がありました。まず該当機器に対応いただけるかというところを重点的に検索しました」
しかし、1社目の診断結果は厳しいものでした。
結果:ハードウェア故障のため対応不可
ただし、この業者からは「さらに細かいところまで確認できる専門業者がいる」という紹介を受けました。
2社目:紹介業者(4月28日依頼)
1社目からの紹介で、Yさんは新たな希望を抱きました。
「1社目からのご紹介で、無償で診断していただけるということでした」
初期の印象も良好でした。
「良い印象でした。2社目のご紹介についても、『確かな技術がありますのでご安心ください』というお言葉をいただきました」
詳細な診断作業
2社目の業者は、1社目よりも踏み込んだ診断を実施しました。
「診断の結果、おそらく制御基盤がダメだというところまでわかったということです。ただ、交換してもどうにもならないということで戻ってきました」
Yさんは、この時点でかなり専門的な診断が行われたと認識していました。
「2社目の方で、かなり詳細なところまで確認していただいたのに...さらに上位の技術って何だろう?という疑問を持ちながら3社目に依頼することになりました」
5月7日、2度目の絶望
診断の結果、復旧不可。この連絡を受けたYさんの心境は、もはや諦めに近いものでした。
「手は尽くされたのではないかと思っていました」
のちにYさんはこう振り返っています。
「ハードディスクの中の分解まではされていないのかなというイメージがありました。技術レベルとしては、そこまでだったのかなという印象です」
最悪の事態への準備
2社目がNGだった時点で、Yさんの組織は方針を転換します。
「2社目がNGだった時点で、諦めないで、最悪の状況を想定して準備しましょうという話になっていました」
具体的には
- 人事部での代替手段の検討
- 失われたデータをどう補填するかの協議
- 5月下旬には業務影響が確実という認識の共有
データの全容が見えない不安
さらにYさんを苦しめたのは、失われたデータの全容が把握できていなかったことでした。
「なくなったデータの全容は、口頭でヒアリングはしていたんですけども、実際に見ていなかったんです。復旧業者に診断していただいて、容量やファイルリストが確認できました。それまでは我々の方で把握ができていなかったので、どれだけの損害があるのかを推し量れない状況でした」
データの重要性は理解していても、その具体的な量や内容が見えない。この状況が、Yさんの不安をさらに増幅させていました。
「3社目をお願いするにあたっては、割とダメ元のような形でしたね」
2社続けての失敗。そして見えないデータの全容。Yさんの1ヶ月に及ぶ悪夢は、まだ終わりが見えない状況でした。
4. 最後の希望 - 3社目への決断
取引先ベンダーへの相談
5月7日、2社目から復旧不可の連絡を受けたYさんは、すぐに行動を起こしました。頼ったのは、日頃から取引のあるベンダーでした。
「弊社で、様々なソリューションや複合機等のお付き合いのある会社さんがいらっしゃいます。そちらに今回の状況についてご相談したところ、データ復旧業者をご紹介いただきました」
紹介されたのが、AOSデータ復旧サービスセンター(DATA119)でした。
複雑な心境
しかし、Yさんの心境は複雑でした。2社の専門業者が「復旧不可」と判断したデータです。
「2社目の方で、かなり詳細なところまで確認していただいたのに...さらに上位の技術って何だろう?という疑問を持ちながら3社目に依頼することになりました」
「手は尽くされたのではないかと思っていました」
それでも、Yさんには選択肢がありませんでした。
「今回3社目をお願いするにあたっては、割とダメ元のような形でしたね」
「復旧できたらありがたいけど、もしかしたらダメかなという気持ちだったんでしょうか」という質問に、Yさんは静かに頷きました。
問い合わせ時の印象
問い合わせは、すべてメールで行いました。
「すべてメールで、ホームページのフォームから入力して送りました」
その時の印象を尋ねると、Yさんは即答しました。
「全く悪くなかったです。良い印象でした」
超特急サービスという選択
Yさんが選んだのは、通常プランではなく「超特急サービス」でした。
「通常の対応ですと2、3週間ということが事前にわかっていました」
なぜ超特急サービスを選んだのか。Yさんの説明は明確でした。
「まず、重要なデータであること。そして、早く結果を知る必要がありました。できるにしてもできないにしても、それを確認するには超特急である必要があったんです」
組織的な意思決定
超特急サービスの利用は、Yさん個人の判断だけでは決められませんでした。
「超特急でいくということを決定するにあたり、人事部長まで確認を取りました」
背景には、社内での報告義務がありました。
「週に一度、組織の部門長、担当執行役員、人事部長にミーティングする機会があります。そのために週次報告をしていました。『ダメだとどうするか』というのを私も聞かれながら結果を待つ、ということが続きました」
Yさんは、上司や役員から「ダメだったらどうするのか」と問われ続ける中で、週次で報告を続けていました。その重圧は相当なものだったはずです。
タイムラインの整理
故障発覚から3社目への依頼までの流れを、Yさんはこう振り返ります。
「初期の故障からですと、1社目に依頼したのが4月21日です。ゴールデンウィークも挟んでいますが、次の2社目に依頼したのが4月28日でした」
「5月7日頃に復旧不可の連絡がありましたので、そこからすぐ付き合いのあるベンダーさんに相談して3社目に。超特急対応としては、1週間あるかないかぐらいですよね」
つまり、5月7日に2社目から復旧不可の連絡を受け、即日DATA119に相談していたのです。
「その早さで優先的にご対応いただけたことに、非常に感謝しています」
諦めに近い気持ちを抱きながらも、Yさんは最後の希望にかけました。それが、1ヶ月に及ぶ悪夢の転機となるとは、この時点では想像もしていなかったことでしょう。
5. 1ヶ月間のプレッシャー
出張先で待つ、暗い知らせ
データ復旧業者への依頼と並行して、Yさんには他のプロジェクトも動いていました。
「同時進行でいくつかプロジェクトが動いていましたし、出張先で結果を知るということが2度も3度もありました」
1社目、2社目からの「復旧不可」の連絡は、いずれも出張先で受け取ることになりました。
「1社目、2社目の時は、かなり暗い気持ちになりましたね」
自責の念
Yさんを苦しめたのは、データ消失そのものだけではありませんでした。
「会社に損害を与えたらどうしよう、という気持ちがありました」
その背景には、NASサーバー設置時の経緯がありました。
「最初、サーバーを建てる時に、やっつけでやったこともありまして。そんなことでデータを失うのは非常に残念だなと」
実は、使用していたNASサーバーは新品ではなく、中古品でした。
「重要なデータまで保管・運用していくという現状を知らずに、手持ちであったNASサーバーが余剰に出ていたものを設置したという...当時の状況を振り返ると、かなり準備不足でした」
「安易に設置してしまったかなと思っていますし、ちょっと安直すぎたかなという反省をしながら過ごしていました」
週次報告という重圧
さらにYさんにプレッシャーをかけていたのは、定期的な報告義務でした。
「週に一度、組織の部門長、担当執行役員、人事部長にミーティングする機会があります。そのために週次報告をしていました」
上司や役員から問われるのは、常に同じ質問でした。
『ダメだとどうするか』というのを私も聞かれながら結果を待つ、というのが続きました」
Yさん自身が定期的に報告していたため、催促はなかったといいます。
「定期的にこちらから報告していますので、特に『まだか、まだか』という話はなかったです」
しかし、それがかえってYさんのプレッシャーになっていました。自ら進んで報告しなければならない立場。それは、責任の重さを常に意識させられる状況でもありました。
ストレスの中での日々
「ストレスというか...なくなったらどれだけの影響が出るのかという想像をしながら過ごしていましたね」
Yさんは、データ消失による影響の大きさを想像しながら、不安な日々を送っていました。
同時進行していた対策
しかし、Yさんは手をこまねいていたわけではありません。万が一復旧できなかった場合に備え、並行して改善策を検討していました。
「今後どういう形で運用していこうか。そこの反省も必要ですので、次は違う方法で人事データを保管していきましょうというところを社内で検討しました。人事部に提案する準備も進めていました」
問題点の整理
Yさんが整理した問題点は、以下の通りでした。
- やっつけで設置したNASサーバー
- 新品ではなく中古品を使用
- バックアップを取る手段がなかった
- 利用実態を把握していなかった
「今回の問題点としては、やっつけで設置していたNASサーバー。しかも、今回故障に至ったNASサーバーは、新品ではなくて中古品だったということです」
「その先にバックアップを取るという手段がなかった。それが反省です」
最悪のシナリオへの準備
人事部では、データが復旧できなかった場合の対応策を検討していました。
「2社目がNGだった時点で、諦めないで、最悪の状況を想定して準備しましょうという話になっていました。人事部の方で、失くしたデータをどういう形で補填するかというところまで準備していただいていました」
プレッシャー、自責の念、そして不確実な未来。Yさんにとって、この1ヶ月間は精神的に非常に厳しい期間でした。3社目にあたるDATA119からの連絡を、Yさんは固唾を飲んで待っていたのです。
6. データ復旧成功の連絡と安堵

復旧成功の連絡
DATA119から「復旧できます」という連絡を受けた時、Yさんの心境はどのようなものだったのでしょうか。
「肩の荷が下りましたね」
その一言に、1ヶ月間のプレッシャーからの解放が込められていました。
「3社目、DATA119さんのお返事をいただいた際は、本当に心の荷が下りたと言いますか」
準備していた最悪のシナリオから逃れられた瞬間でした。
「準備していたことがいろいろございましたし、最悪の状況から逃げられたと」
2社の専門業者が復旧不可と判断したデータ。人事部では補填策を検討し、週次で役員に報告を続け、自責の念に苛まれながら過ごした日々。そのすべてから解放される瞬間でした。
データの完全性を確認
そして、復旧完了後に送られてきたファイルリストを確認した時――
「いかにも弊社で扱うようなデータの文字列が並んでいました。確実にこの状態で復旧できる、文字化けもしていないというところも視覚的にわかりました」
データは完全に復旧していました。損失はほぼゼロ。
「その瞬間、『大丈夫だった』と、深呼吸みたいな形で息を吸い込みました」
Yさんの胸に去来したのは、安堵だけではありませんでした。
「サーバーを設置していたものとしては、過失の部分もありましたので、その部分が非常に救われたという感情でした」
驚異的なスピード
Yさんを驚かせたのは、復旧の成功だけではありませんでした。
「あまりにも早くて驚きましたね。もう2週間、場合によっては3週間かかると思っていたんです」
復旧までの期間
- 依頼から復旧成功の連絡まで:約1週間
- 納品まで:1〜2日
時系列を整理すると
- 5月7日:2社目から復旧不可の連絡
- 即日:DATA119に相談
- 約1週間後:復旧成功の連絡
- 1〜2日後:納品(5月中旬)
なぜこのスピードが実現できたのか
Yさんは、復旧の背景にある体制について尋ねました。
「体制を整えていただいたと聞きましたが、ハードディスク1台に何人も作業で入られるんですか?人件費、技術費がかなりかかっているイメージがあります」
DATA119の担当者からの説明で、Yさんは納得しました。
「ハードディスクの造詣が深い方とか、専門の方とかがいらっしゃる。できる限り早くお答えするために、かなり人員を割いていただいたと思います」
DATA119の体制
- 専用のラボを用意
- 復旧する道具や設備を完備
- 複数の専門技術者を投入
納品後も問題なし
「不具合はございませんでした」
Yさんは納品されたSSDから、すぐに対策を講じました。
「早速、納品いただいたSSDから、さらにハードディスクを1台追加で用意しまして、そこでバックアップを取りました。特に納品後の問題はなかったです」
技術力への評価
2社の専門業者が「復旧不可」と判断したデータを、わずか1週間で復旧したDATA119。Yさんの評価は明確でした。
「専用のラボで技術者が復旧作業をされていると聞きました。本当に助けられました」
当初、Yさんが抱いていた「さらに上位の技術って何だろう?」という疑問。その答えは、ハードディスクの分解レベルまで踏み込んだ高度な技術力と、迅速な対応を可能にする専門的な体制にありました。
1ヶ月に及ぶ悪夢が、ようやく終わりを迎えようとしていました。
7. サービスへの評価
ベストな対応
復旧が成功し、データも手元に戻ったYさん。DATA119のサービスをどう評価したのでしょうか。
「ベストな対応だったかと思います」
その評価は明確でした。
分かりやすい報告
特に印象的だったのは、報告の分かりやすさでした。
「データの復旧状況であったり、データの一覧であったり、そういったものの、確実に顧客が見て分かるような結果を出していただいた。非常に良い印象がありましたし、分かりやすかったです」
ファイルリストを確認した際、Yさんは視覚的にデータの状態を把握できました。これは、技術者ではない立場の人間にとって、非常に重要なポイントでした。
透明性のある料金体系
超特急サービスを利用したYさんですが、料金面での不満はありませんでした。
「超特急の料金も、特に不明瞭なところはございませんでしたし、密に連絡していただいたかと思います。我々の方から何も申し上げることがないです」
柔軟な対応
さらにYさんが評価したのは、柔軟な対応でした。
「今回、特例で、納品期限を対応していただいたというところまでやっていただいています」
当初、DATA119側から納品時期について事前に確認がありました。しかし、会社の都合で調整が必要になった際も、柔軟に対応してもらえました。
「こちらもお手数をおかけしましたが、納品期限まで対応いただいて、法人向け対応としても全く問題ないところでございまして」
法人対応への評価
Yさんは、DATA119が法人顧客への対応に慣れていると感じました。
「普段は一般の方への対応のほうが多いかと思うんですけど、法人対応の準備もきっちりしていただいているというところがありますので、我々としては非常に感謝しております」
完全成功報酬型への評価
DATA119は、復旧できなかった場合は料金を取らないという「完全成功報酬型」のシステムを採用しています。この料金体系について、Yさんはどう感じたのでしょうか。
「適切だと思います」
Yさんの評価は明快でした。
「特に超特急の診断の部分で、別途料金をいただくということでご説明もいただいていましたし、早く結果を知りたいと思いますので、そこの費用については納得していました」
業界の傾向
実は、Yさんが依頼した1社目、2社目も同様に成功報酬型でした。
「成功報酬というところは、各社とも自信の現れみたいなものがあるのではというところで、我々もそこを信じてお願いしていたという背景がございました」
Yさんは、成功報酬型を採用する理由について、こう推測しています。
「会社さんとしては、新規のお客様との信頼性というところをアピールされるのかわかりませんけれども、そういった観点で成功報酬型にされているのかなという印象を持っていました」
「もし成功報酬型でなかったら、依頼するつもりはなかったですか?」という質問に、Yさんはこう答えています。
「3社目の段階では、『難しいというのは、ハードディスクがダメなんだね』という感じになっていました」
つまり、3社目の時点では、成功報酬型であることが依頼の前提条件ではなかったということです。しかし、1社目、2社目を選ぶ段階では、成功報酬型であることを重視していました。
「どの会社さんもやはり、成功報酬型ということで、診断料を基本的にいただかないという形になっていました」
この料金体系が、データ復旧業界における標準的なビジネスモデルとなっていることが分かります。そして、それは顧客にとって「復旧できなければ費用はかからない」という安心感を提供する仕組みでもあるのです。
8. 再発防止と教訓
根本原因の振り返り
データ復旧に成功したYさんですが、今回の経験を無駄にはしませんでした。問題の根本原因を冷静に分析し、抜本的な改革に着手したのです。
設備面の課題
まず明らかになったのは、設備面での問題でした。
「今回の問題点としては、やっつけで設置していたNASサーバー。しかも、今回故障に至ったNASサーバーは新品ではなくて中古品だったということです」
設備の課題
- 中古のNASサーバーを使用
- バックアップ体制の欠如
- 世代管理の仕組みなし
運用面の課題
さらに深刻だったのは、運用面での課題でした。
「人事部は『フォルダがあるから使いましょう』という感じになっていて、そのフォルダの先がサーバーであるということを、実は知らない者もいました」
運用の課題
- 利用実態の把握不足
- ユーザー教育の不足
- データの重要度認識の甘さ
抜本的な改革
Yさんの会社では、システムごとにバックアップ体制に差がありました。
「他のシステムはバックアップの手段が充実していまして、最終的にクラウドからもバックアップを取り入れている状況です」
一方、今回問題が発生した人事専用NASは――
「この専用NASには、バックアップを取る手段がありませんでした。直接データを取り出したり保管できたりするという便利さはあったんですけど、それではバックアップ体制に関しては全く薄いと言いますか、ほとんどない状態でした」
便利さを優先した結果、リスク管理が疎かになっていた――これがYさんの反省でした。
新しいバックアップ体制の構築
Yさんは、今回の反省を踏まえて、抜本的な改革を実施しました。
「今回の反省点を踏まえまして、人事端末からのデータを最終的にクラウドへ保管するという方向性に変更しました」
新しいバックアップ体制
- 人事端末のデータを定期的にバックアップ
- クラウドに保管
- セキュアな環境を維持
「人事部だけが見れる環境を構築した上で保管・バックアップができるように方向性を変えました」
この改革により、以下が実現されます
- バックアップが確実に取れる仕組み
- 世代管理ができる仕組み
- クラウドへの保管
「そういった仕組みをまずは整えましょうということを同時に進行しております」
運用の見直し
設備だけでなく、社内教育も改善の対象となりました。
「仕組みをちゃんと理解してもらおうというところを、今回構築し直すにあたり説明することにしました」
データがどこにあり、どのように保管されているのか。利用者がその仕組みを理解することで、データの重要性への認識も高まります。
今回のデータ消失における教訓
今回の経験を通じて、Yさんが最も強く感じたこと――
「もうちょっとちゃんと準備すればよかった」
「運用が変わったというのもあるんですけども、やはりいかなる時もバックアップ体制を整えておかないといけない」
準備不足、安直な判断、利用実態の把握不足。これらの反省が、抜本的な改革へとつながりました。
1ヶ月に及ぶ悪夢は、組織にとって貴重な教訓となったのです。
9. 同じ状況に陥った方へのアドバイス
1ヶ月に及ぶ格闘を経験したYさん。同様のトラブルに直面する可能性のある、全国の情報システム担当者へ向けて、貴重なアドバイスを送ります。
トラブル発生時の心構え
「やはり落ち着くことですね」
Yさんが最初に強調したのは、冷静さを保つことの重要性でした。
「何ができるのかというところをまず冷静に判断して、どこまでできるかというのを、自分の限界を切り分けるところで。ものすごく焦って二次災害を起こさないようにしていただければと思います」
データが消失した瞬間、パニックに陥るのは自然なことです。しかし、その焦りが二次災害を引き起こす可能性があります。
まず深呼吸して、冷静に状況を把握する――これがYさんからの第一のアドバイスです。
絶対にやってはいけないこと
Yさんが特に強調したのは、知識のない状態での自己判断の危険性でした。
「ハードディスクに変更を加える、例えば変な外部機器を接続してデータだけ見れるんじゃないかとか、ちょっと分解してみましょうとか、知識がないのにできるだけやってみましょうというところを手広くされるのは、やはり失敗の確率が高いのではないかと思っています」
NG行動リスト
- ハードディスクに変更を加える
- 外部機器を接続してデータを見ようとする
- 知識がないのに分解してみる
- 「できるだけ自力でやってみよう」と手を広げる
これらの行動は、復旧の可能性を下げるだけでなく、完全にデータを失う危険性すらあります。
正しい対応とは
では、どうすべきか。Yさんの答えは明確です。
「起こった状態、手つかずの状態で業者様に診断を出して、確実にやっていただくというのが良いのかなと感じました」
現状を維持したまま、専門家に任せる――これが正解です。
「他社様がそういった状況に陥った場合は、そうしていただいた方がよいのかなという思いがあります」
復旧業者の選定方法
1. 取引のあるベンダーからの紹介を活用
Yさんが最も推奨するのは、信頼できるベンダーからの紹介です。
「やっぱり、そういったベンダー様、お付き合いのあるベンダー様のご紹介というのは非常に強いのかなと思いました」
その理由は?
「そういった対応をベンダー様もよく受け付けていたということで、よくお客様からの相談があるということで事例があるので、やはりノウハウをいくつか持っていらっしゃるというところですね」
取引のあるベンダーは
- 同様のトラブル事例を扱った経験がある
- 信頼できる復旧業者を把握している
- 顧客の状況を理解した上で紹介してくれる
今回、Yさんが付き合いのあるベンダーからの紹介でDATA119にたどり着いたのも、この経路でした。
2. 複数の情報源から収集
ただし、ベンダーからの紹介だけに頼るのではなく、幅広く情報を集めることも重要です。
「ネットで探すというところも、今回我々、最初の一歩でしたけど、持っている視野が違うという方もいらっしゃいますので、いろんなところで情報を収集されるのがよいのかなと思います」
Yさんの経験
- 1社目:インターネット検索で発見
- 2社目:1社目からの紹介
- 3社目(DATA119):取引ベンダーからの紹介
それぞれの経路で得られる情報は異なります。複数の情報源を活用することで、より適切な業者を見つけられる可能性が高まります。
3. 完全成功報酬型の安心感
業者選定の一つの指標として、Yさんは「完全成功報酬型」を挙げています。
「成功報酬というところは、各社とも自信の現れみたいなものがあるのではないかということで、我々もそこを信じてお願いしていたという背景があります」
復旧できなければ料金を取らない――このシステムは、業者の技術力への自信の表れでもあります。
Yさんからのデータ復旧サービスを選ぶ際のアドバイス
1ヶ月間の悪夢を経験したYさん。しかし、その経験は組織に貴重な教訓をもたらしました。
落ち着いて、現状を保ち、専門家に任せる。
シンプルですが、これが最も確実な方法です。
そして、復旧業者を選ぶなら
- 信頼できるベンダーからの紹介を検討する
- 複数の情報源から情報を集める
- 成功報酬型かどうかも一つの指標にする
「いろんなところで情報を収集されるのがよいのかなと思います」
Yさんの経験が、同じ状況に陥った方々の助けとなることを願っています。
10. ビジネスへの影響
ギリギリのタイムリミット
データが復旧し、すべてが元に戻ったように見えます。しかし、実際のビジネスへの影響はどうだったのでしょうか。
「今回のデータ消失で失われた影響は大きいです」
Yさんの言葉には重みがありました。
「影響自体はすぐには出なかったですが、必要になるということで、いつ必要になるか確認したところ、5月下旬ぐらいには要るだろうという話を人事部からお聞きしていました」
タイムラインを振り返ると
- 4月中旬: 故障・データ消失の発覚
- 4月21日: 1社目に依頼
- 5月7日: 2社目から復旧不可の連絡、即日DATA119に相談
- 約1週間後: 復旧成功の連絡
- 5月中旬: データ納品
- 5月下旬: データが必要になるタイミング
「そこまでにもし何もなかったら影響が出ていた可能性はあります」
もし復旧が5月下旬を過ぎていたら、業務への影響は避けられませんでした。
もし復旧できなかったら
では、もし3社目のDATA119でも復旧できなかったら、どうなっていたのでしょうか。
「今回解決しなかった場合は、準備していた内容がいくつかあるんですが、そちらの着手に入っていたかなと思います」
人事部では、データが復旧できなかった場合の代替手段を準備していました。しかし、それは容易な作業ではありません。
想定されていた代替作業
- 失われたデータの再作成
- 外部組織からの問い合わせへの対応方法の変更
- 採用関連データの再収集
これらの作業には、膨大な時間とコストがかかったはずです。
影響範囲の特殊性
興味深いのは、影響範囲が限定的だったという点です。
「これは人事部に関して影響が出ていたというところでありましたが、会社全体としては、影響としてはなかったという内容になります」
人事専用NASという特殊な環境で、限られた端末のみがアクセスできるシステム。そのため、影響は人事部門に集中していました。しかし、だからといって影響が小さいわけではありません。人事データは企業の根幹を支える機密情報です。その消失は、組織の信頼性そのものに関わる問題でした。
復旧できたことの意味
結果として、データは完全に復旧しました。
「データの損失がほとんどなかったので、サーバーを設置していたものとしては、過失の部分もありましたが、非常に救われたという感情でした」
時間との戦いに勝った意味
もし復旧が5月下旬を過ぎていたら、業務への影響は避けられませんでした。DATA119の超特急サービスによる迅速な対応が、この時間との戦いに勝利をもたらしたのです。
超特急サービスを選択した判断の正しさ
- 通常対応:2〜3週間
- 超特急対応:約1週間
この1〜2週間の差が、ビジネスへの影響の有無を分けました。
「早く結果を知る必要がありました。できるにしてもできないにしても、それを確認するには超特急である必要があったんです」
人事部長まで確認を取って決断した超特急サービス。その判断は、結果として正しかったのです。
見えない損害の回避
データ復旧によって回避できたのは、目に見える業務への影響だけではありません。
回避できた潜在的な損害
- 社内での信頼性低下
- 情報システム部門への評価低下
- データ管理体制への不信感
- 代替作業に伴う人的コストの増大
- 外部組織への対応遅延による信頼性への影響
「会社に損害を与えたらどうしよう、という気持ちがありました」
Yさんが抱いていたこの不安は、DATA119によって杞憂に終わりました。しかし、その緊迫感は、データの重要性を物語っています。
今回の経験から得られた教訓
バックアップの重要性は、データが失われてから気づくのでは遅い。Yさんは、この経験を無駄にせず、抜本的なバックアップ体制の構築に着手しました。それは、同じ悪夢を二度と繰り返さないための、組織としての決意の表れです。
11. まとめ:データ消失から学んだこと
1ヶ月の悪夢が残したもの
2025年4月中旬から5月中旬にかけて、Yさんは1ヶ月間に及ぶ格闘を経験しました。基幹系NASサーバーの故障によるデータ消失。2社の専門業者による復旧不可の診断。週次で役員に報告を続ける重圧。自責の念。そして、5月下旬というタイムリミット。
しかし、3社目のAOSデータ復旧サービスセンター(DATA119)による復旧により、この悪夢は終わりを迎えました。この経験から、Yさんは何を学んだのでしょうか。
データ管理の重要性
今回の経験を通じて、Yさんが痛感したのは以下の点です。
1. バックアップ体制は必須
- 単一のストレージに依存しない
- 世代管理が可能な仕組み
- クラウドの活用
「その先にバックアップを取るという手段がなかった。それが反省です」
2. 利用実態の正確な把握
- どのようなデータが保存されているか
- 誰がどのように利用しているか
- データの重要度の正確な評価
「利用実態を我々も把握しておらず、かなり大事なデータだということで驚きました」
3. 定期的な見直しと改善
- 運用の変化に応じた見直し
- ユーザー教育の徹底
- 設備の適切な管理
「仕組みをちゃんと理解してもらおうというところを、今回構築し直すにあたり説明することにしました」
Yさんが実施した抜本的改革
理論だけではなく、Yさんは実際に行動を起こしました。
新しいバックアップ体制
- 人事端末のデータを定期的にバックアップ
- クラウドに保管
- セキュアな環境を維持しながら世代管理を実現
- 人事部だけが見れる環境の整備
「人事部だけが見れる環境を構築した上で保管・バックアップができるように方向性を変えました」
専門家への信頼
Yさんが強調するのは、自己判断の危険性と、専門家への信頼の重要性です。
「もうちょっとちゃんと準備すればよかった。運用が変わったというのもあるんですけども、やはりいかなる時もバックアップ体制を整えておかないといけない」
自己判断での対応は危険であり、適切な業者選定が成功の鍵となります。完全成功報酬型という料金体系は、その自信の表れでもあります。
組織的な対応の重要性
今回の危機を乗り越えられたのは、組織的な対応があったからこそです。
組織的な対応のポイント
- 部門間の連携(情報システム部門と人事部)
- 経営層への適切な報告(執行役員、部長レベル)
- 最悪のシナリオへの備え(代替手段の準備)
「週に一度、組織の部門長、担当執行役員、人事部長にミーティングする機会があります。そのために週次報告をしていました」
Yさんからのメッセージ
最後に、Yさんから同じ状況に直面する可能性のある、すべての情報システム担当者へのメッセージです。
落ち着いて、冷静に
「今回の経験で、データの重要性とバックアップ体制の必要性を痛感しました。同じような状況に陥られた方は、まず落ち着いて、自分の限界を見極めて、信頼できる専門家に相談することをお勧めします」
二次災害を起こさない
「焦って二次災害を起こさないこと。起こった状態、手つかずの状態で業者様に診断を出して、確実にやっていただく。それが一番良いと感じました」
諦めない
「諦めずに適切な対応をすれば、道は開けます」
2社の専門業者が「復旧不可」と判断したデータ。それでもYさんは諦めませんでした。3社目に相談し、超特急サービスを選択し、結果として完全復旧に成功しました。
最後に
データ消失のリスクは、どの企業にも存在します。完璧なシステムは存在しません。重要なのは、リスクを認識し、適切な備えをし、万が一の際には冷静に対応することです。
Yさんの1ヶ月間の悪夢は、多くの教訓を残しました。
- 事前の備え: バックアップ体制の構築
- 発生時の対応: 冷静な判断と専門家への相談
- 事後の改善: 抜本的な改革の実施
この記事が、同様の課題に直面する企業や担当者の方々の助けとなれば幸いです。データは企業の財産です。失ってから気づくのでは遅い。今、できることから始めましょう。
お客様の不安に寄り添うデータ復旧サービスとして
私たちは日々、データ復旧のご相談をいただいていますが、どのお客さまも大切なデータを失われた不安の中でお問い合わせくださっています。だからこそ、まずはお客様のお話にしっかりと耳を傾けることを大切にしています。
今回のYさんのように、諦めずにご相談いただき、最終的に「復旧できてよかった」と感じていただけたことは、私たちにとっても本当に嬉しいことでした。
2社で復旧不可と言われた後のご不安は、相当なものだったと思います。それでも「超特急サービス」を選択され、社内への影響を最小限に抑えられたYさんのご判断には、敬意を表します。
今回のご依頼を通じて、改めて「お客さまの状況を的確に把握すること」の重要性を実感しました。この経験を活かし、今後もより良いサービスをお届けできるよう努めてまいります。
この度は、DATA119をお選びいただきありがとうございました。
担当コンサルタント:平木